「ハーフタイム〜成功から意義へ〜」
50歳を過ぎた人生の後半戦における書くことの重要性についてものつくり大学 井坂康志教授をゲストとして招いてオンライン講座を開催。井坂教授の自身の25年間の出版社での経験を基に、書籍出版における編集者の重要な役割や本の出版プロセスについて詳しく説明し、企画から完成までの具体的な事例を共有していただいた。講座の最後には、書くことの価値やAIの活用について質疑応答が行われた。その講座の概要と映像を共有する。
講師プロフィール

マネジメントの父 ピータードラッカーの専門家
ものつくり大学教養教育センター教授/NPO法人ドラッカー学会共同代表井坂康志氏
1972年埼玉県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、現在ものつくり大学教養教育センター教授、図書館メディア情報センター長。NPO法人ドラッカー学会共同代表。2005年、最晩年のドラッカーに自宅で会い、インタビューを行った経験を持つ。
50歳を過ぎたら本を書け!その真意とは?
〜人生の後半戦 50代からはじめる初めての出版〜
2025年8月2日(土)にオンラインに開催したその動画はこちら
オンライン講座の概要
人生後半戦を豊かにする「書く力」──出版で広がる40代・50代のキャリアと生き方
2025年8月2日、弊社主催のオンライン講座「ハーフタイム──成功から意義へ」にて、人生後半のキャリア戦略と自己実現における“書くこと”の価値をテーマに、ピーター・ドラッカー研究者であり編集者の井坂康志教授をお迎えしました。
主催の吉田真は、余命宣告を受けながらも活動を続ける自身の経験を語り、「限られた時間をどう使うか。その選択肢のひとつとして“書くこと”は大きな意味を持つ」と述べました。
書籍出版は資格不要、しかし容易ではない
井坂教授は、25年間の出版社勤務経験から、**「出版は資格のない世界だが、参入のハードルは高い」**と指摘しました。
必要なのは「最後まで書ききる覚悟」と「適切なマインドセット」。良い原稿だけでは十分ではなく、読者ニーズに応える視点と、編集者との緊密な連携が成功の鍵となります。
編集者は“舞台監督”──著者との二人三脚
出版の現場で編集者は、著者の想いを形にし、読者に届く舞台を整える存在です。
井坂教授は「優れた内容だけで本は売れない。編集者が舞台を整え、著者がその舞台で演じる」と例え、編集者をパートナーとして尊重する姿勢の重要性を強調しました。
出版の道をひらく4つの条件
商業出版の門戸は狭く、原稿持ち込みを受け入れる出版社はわずかです。井坂教授は、出版実現のために以下の条件を挙げました。
- 企画書の完成度(テーマの明確さと構成力)
- 独自性(他と差別化できる視点)
- 社会的関連性(時代や社会との接点)
- 著者の業績・略歴の整備(信頼性を高める情報更新)
3年かけて生まれた『ピータードラッカーの実像』
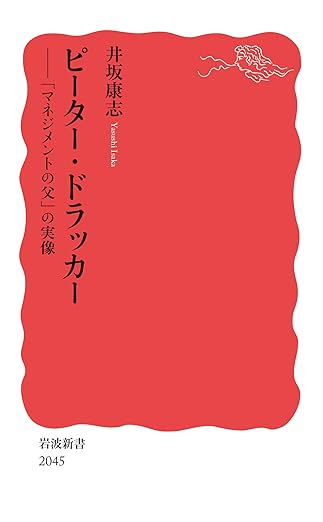
井坂教授が手掛けた『ピータードラッカーの実像』(岩波書店)は、2020年の企画から出版まで約3年。
ターゲットをあえて「ドラッカーを嫌う人」に絞る戦略や、複数回の編集会議・審査など、出版の舞台裏が語られました。
AI時代の“書くこと”の新しい形
質疑応答では「AIをどう活用するか」という問いが寄せられ、井坂教授は「AIは積極的に使うべき」と回答。構成づくりや文章の整理など、AIをツールとして取り入れることで、著者は創造力に集中できると述べました。
人生の折り返し地点でこそ“書く”という選択を
講座の最後に、井坂教授は今後の執筆テーマとして「ハーフタイムの研究」と「石橋湛山の伝記」に取り組む計画を発表。吉田は「書くことは、経験や思いを未来へ手渡す行為」と語り、参加者にエールを送りました。
人生の後半を迎える40代・50代にとって、“書くこと”は自己表現であり、社会との新たな接点を生む行動です。キャリアの集大成として、自分の言葉で未来を紡ぐ一歩を踏み出してみませんか。
コメント